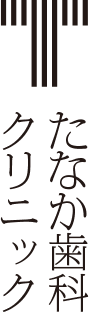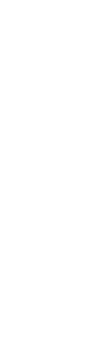あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願い申し上げますm(*_ _)m
歯の着色はコーヒーだけじゃない!
— 意外な原因と、今日からできる着色予防のコツ —
というお話をしたいと思います。

「最近、歯が黄色く見える気がする」「前より着色が落ちにくい」
そんな相談はとても多いです!
そして多くの方が「コーヒーのせいかな」と思っていますが、実は着色の原因はコーヒーだけではありません。
この記事では、歯の着色を引き起こす意外な原因と、今日からできる予防のコツをわかりやすくまとめました。
ホワイトニングをしていない方にも、している方にも役立つ内容です。
◎歯の着色には2種類ある
まず知っておきたいのは、着色には大きく2種類あるということです。
①外側につく着色(外因性)
食べ物・飲み物・タバコなどによる表面の汚れ。
クリーニングで落とせることが多い。
⓶歯の内部が変色する着色(内因性)
加齢・薬剤・神経の変化などが原因。
ホワイトニングや被せ物での対応が必要なことも。
この記事では、特に多い「外因性の着色」を中心に解説します( • ̀ω•́ )b
コーヒー以外にもある“意外な着色の原因”
① お茶(特に緑茶・紅茶・ウーロン茶)
実はコーヒーよりも着色しやすいことがあります。
お茶に含まれる「タンニン」が歯の表面に付着しやすいためです。
② スポーツドリンク・炭酸飲料
色が薄くても油断できません。
酸性度が高く、歯の表面をわずかに溶かして“着色がつきやすい状態”を作ります。
③ カレー・ミートソース・キムチ
色素が強く、歯の表面に残りやすい食品。
特にホワイトニング直後は吸着しやすく要注意。
④ マウスウォッシュ(クロルヘキシジン系)
殺菌力が高い一方で、長期使用すると着色しやすいタイプがあります。
医療用のものを使っている方は注意が必要です。
⑤ タバコ(紙・電子どちらも)
ヤニだけでなく、ニコチンが歯の表面に沈着しやすく、着色のスピードが速いのが特徴です。
⑥ 口の乾燥(ドライマウス)
唾液が少ないと汚れが流れにくく、着色が定着しやすくなります。
意外ですが、乾燥は着色の大きな原因です。
☆今日からできる着色予防のコツ
① 色の濃い飲み物は“飲み方”を工夫する
・だらだら飲まず、時間を決めて飲む
・飲んだ後に水をひと口飲む
・ストローを使うと前歯の着色が減る
これだけで着色のスピードが大きく変わります。
② 食後すぐに歯を磨かなくてもOK
酸性の飲食後すぐのブラッシングは、逆に歯を傷つけることがあります。
30分ほど時間を置いてから優しく磨くのがベストです。
③ 歯の表面を傷つけないケアを選ぶ
研磨剤が強すぎる歯磨き粉は、表面を削って着色がつきやすい状態を作ります。
「低研磨」「ステインケア」などの表示を目安に選びましょう。
④ 唾液を増やす習慣をつける
唾液は天然のクリーニング剤。
・キシリトールガム
・こまめな水分補給
・鼻呼吸の習慣
これらは着色予防にも効果的です。
⑤ 定期的なクリーニングで“リセット”する
家庭のケアでは落としきれない着色は、歯科のクリーニングでしっかり除去できます!
特に、
・お茶やコーヒーを毎日飲む
・タバコを吸う
・ホワイトニングをしている
という方は、3〜6ヶ月に1回のクリーニングがおすすめです。
まとめ:着色は“生活のクセ”で変わる
歯の着色は、ちょっとした習慣の積み重ねで大きく変わります。
・飲み方を工夫する
・食後すぐ磨かない
・低研磨の歯磨き粉を使う
・唾液を増やす習慣をつける
・定期的にクリーニングでリセット
これらを意識するだけで、着色のスピードは確実にゆるやかになります。
「ホワイトニングをしていないけど白く保ちたい」
「着色が気になってきた」
そんな方は、ぜひ今日から取り入れてみてくださいね(﹡ˆ﹀ˆ﹡)ノ
こんにちは。
あっという間に今年も終わってしまいますね(´⊙ω⊙`)
本格的に寒くなってきたので、暖かくしてお過ごしください(*˘︶˘*)
さて今日は、子どもの「おやつ選び」で虫歯リスクを半分にする具体ルールをお話したいと思います。
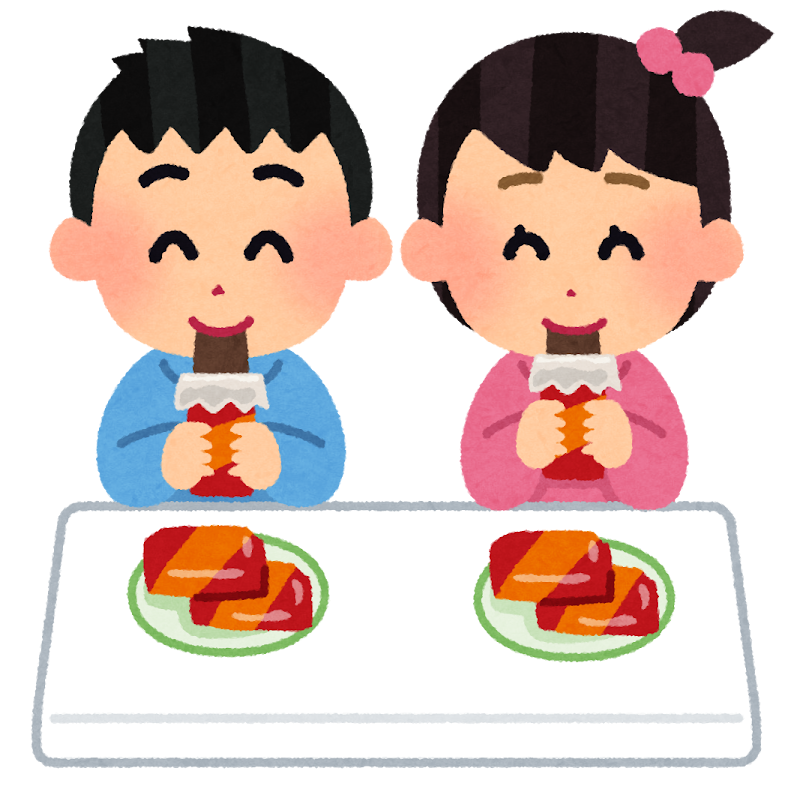
— 保護者が今日からできる、シンプルで続けやすい習慣 とは?
子どもの虫歯は「歯磨き不足」だけが原因ではありません。
実は、おやつの選び方と与え方が虫歯リスクを大きく左右します。(。•̀ω-)
同じ量の砂糖でも、食べ方やタイミングによって虫歯のなりやすさは大きく変わります。
この記事では、保護者の方がすぐに実践できる「虫歯リスクを半分にするおやつのルール」をわかりやすく紹介します!
■ なぜ“おやつ”で虫歯が増えるのか
虫歯菌は、糖をエサにして酸を作り、その酸が歯を溶かします。
ポイントは「どれだけ砂糖を食べたか」よりも、どれくらいの時間、口の中が酸性になっているかです。
つまり、
- 砂糖が少なくても“ダラダラ食べ”
- 飲み物でずっと甘いものを飲む
- 粘着性の高いお菓子を頻繁に食べる
こうした習慣があると、歯は長時間酸にさらされ、虫歯が進みやすくなります(゚Д゚)
■ 今日からできる「おやつ選び」5つのルール
① おやつは“時間を決めて”食べる
虫歯予防で最も効果があるのは、ダラダラ食べをやめることです。
時間を決めて食べれば、歯が酸にさらされる時間が短くなり、自然に唾液が歯を修復する時間が確保できます。
おすすめは1日1〜2回、15〜20分以内!
これを目安にしてみてください(*´︶`*)
② 飲み物は「水かお茶」が基本
ジュース・スポーツドリンク・乳酸菌飲料は、砂糖が多いだけでなく、酸性度が高いものも多く、歯を溶かしやすい特徴があります。
「おやつは甘くても、飲み物は甘くしない」
これだけで虫歯リスクは大きく下がります。
③ “歯にくっつく”お菓子は頻度を減らす
キャラメル、グミ、ソフトキャンディ、スナック菓子などは、歯に残りやすく虫歯リスクが高めです。
どうしても食べる日は、
- 食後に食べる
- その後に水を飲む
- できれば歯磨き or うがい
これだけでダメージを軽減できますよ( •̀ᴗ•́ )و ̑̑
④ 虫歯になりにくい“おやつの種類”を知る
虫歯になりにくいおやつは、砂糖が少ない・歯に残りにくい・噛む回数が増えるものです。
おすすめ例:
- チーズ
- ナッツ(小さい子は誤嚥に注意)
- さつまいも・とうもろこし
- おにぎり
- ヨーグルト(無糖 or 低糖)
- 果物(食べすぎ注意)
「甘いもの禁止」ではなく、“選び方”を工夫するだけでOKです。
⑤ 食べ終わったら“口をリセット”する
歯磨きができない外出先でも、
- 水を飲む
- うがいをする
- ガム(キシリトール100%)を噛む
これだけで口の中の酸性状態が中和され、虫歯リスクが下がります。
■ よくある質問(保護者の方から)
Q. 甘いものは完全に禁止したほうがいい?
A.禁止する必要はありません。大切なのは「量より頻度」。
“食べる回数”を管理するほうが虫歯予防に効果的です。
Q. 果物は甘いけど大丈夫?
A.食べすぎなければOK。果物は水分が多く、歯に残りにくいのでお菓子より虫歯リスクは低めです。
Q. 食後に甘いものを食べるのは良い?
A.とても良い選択です。
食後は唾液が多く出ているため、虫歯リスクが下がります。
■ まとめ:おやつの“選び方”で虫歯は防げる
子どもの虫歯は、毎日の小さな習慣で大きく変わります!
- 時間を決めて食べる
- 飲み物は水かお茶
- 歯に残りにくいおやつを選ぶ
- 食後に甘いものをまとめる
- 食べた後は口をリセット
この5つを意識するだけで、虫歯リスクは確実に下がります。
「甘いものを楽しみながら、虫歯を防ぐ」
そのためのコツを、ぜひ今日から取り入れてみてください( •̀∀•́ )b
こんにちは。
皆さんはお口の乾きが気になったことはありませんか?
口の渇きは「たんなる乾き」ではありません。
唾液は歯を守り、食べ物を飲み込みやすくし、口臭を抑える重要な働きを持っています。
唾液が減ると虫歯や歯周病、嚥下の問題、睡眠の質低下につながることがあるため、早めの気づきと簡単な対策が大切です。

今回は患者さんがすぐに実践できるチェック方法と生活で続けやすい対処法をお伝えします(*´∀`*)!
★気づきのサイン(まず自分で確認すること)
- 朝、口がべたついたり激しく乾いている
- 食事中に唾液がほとんど出ないと感じる
- 1時間に何度も飲み物を欲する習慣がある
- 舌や唇にひび割れや白っぽい膜がある
- 常用薬(抗ヒスタミン、抗うつ薬、利尿薬など)が多い、あるいは糖尿病や自己免疫疾患がある
これらのうち2つ以上あてはまる場合は生活習慣の見直しを始めてください。改善が見られないときは専門受診を検討します。
★今日からできる実践的な対策(続けやすさ重視)
- こまめに少量の水を飲む
- 一気に大量を飲むより「少量を頻回」にすることで唾液分泌を刺激します。外出時は携帯ボトルを持つ習慣を。
- 食後にキシリトールガムを噛む(5〜10分)
- 噛むことで唾液が増え、虫歯リスクも下がります。顎に負担がある人は噛む時間を短めに。
- 就寝前の習慣を整える
- 就寝1時間前からカフェイン・アルコールを控える。寝室の加湿は40〜60%を目安にし、口が開きにくい枕の高さを試すと改善することがあります。
- 低刺激の保湿製品を活用する保湿スプレーや唾液代用品、就寝時用ジェルなどを状況に応じて使用します。刺激の強い成分が入っていない製品を選んでください。
- 口腔ケアは丁寧に、でも優しく(*´︶`*)
強い摩擦は避け、低研磨の歯磨剤とフッ化物を使って正しくブラッシングします。うがいはやりすぎないことが大切です。
★見直すべき生活要因と薬剤の確認
- 喫煙は唾液分泌を低下させます。可能なら禁煙支援を検討してください。
- 抗ヒスタミン薬、抗コリン作用を持つ薬、利尿薬などが原因になることがあります。薬を自己判断で止めず、処方医と相談してください。
★受診の目安(早めに相談すべき場合)
- 数週間のセルフケアで改善しないとき
- 口の中に痛みや白い膜、出血があるとき
- 嚥下でむせる、体重が減っている、誤嚥性肺炎が疑われるとき
★歯科で受けられる診察と主な対応
- 問診と口腔の視診、簡易的な唾液量の測定を行います
- 保湿剤や唾液分泌促進薬の提案、唾液腺マッサージや義歯調整、口腔衛生指導を実施します
- 必要に応じて耳鼻科や内科と連携して全身要因を調べます
1週間試してみるプランは?
- 毎朝・昼・夜に水を少量ずつこまめに飲む習慣をつける
- 食後1回、キシリトールガムを噛む
- 就寝1時間前からカフェイン・アルコールを控え、就寝前に保湿ジェルを使用する
1週間続けて変化がなければ受診を検討してください
FAQ(患者向け簡潔回答)
- Q: キシリトールガムは毎日使っていいですか
- A: 唾液促進と虫歯予防に有効です。噛みすぎで顎に負担がかからないよう気をつけてください。
- Q: ドライマウス用の保湿スプレーは安全ですか
- A: 低刺激タイプであれば就寝前などに短期使用で効果が期待できます。使用説明に従ってください。
- Q: どれくらいで改善しますか
- A: 原因によりますが、生活習慣の改善で数週間以内に自覚改善が見られることが多いです。
ドライマウスは、歯や身体にとって様々な影響をもたらす可能性があります。
飲んでいる薬の副作用や、病気の症状として出る場合もあります。
まずはセルフチェックをしてみて、できる対策をしていきましょう(*゚▽゚)ノ
こんにちは。
11月に入りぐっとさむくなりましたね。
インフルエンザも流行っているみたいなので、お気を付けください(*ᴗˬᴗ)⁾
今日は、歯がしみる原因や応急ケアについてお話したいと思います。
歯がしみる症状は軽微な知覚過敏から重篤な歯髄炎まで原因が幅広く、対処法と受診のタイミングが異なります。
どういった症状なのか、こちらの記事で確認してみてくださいね!
◎痛みのタイプ別にまずチェックすること
●刺激で一瞬だけ「キーン」としみる
多くは知覚過敏や楔状欠損。刺激がなくなると症状も消えることが多い。
●冷たいものには反応せず、熱いもので長く痛む
歯髄炎(神経の炎症)の可能性があり注意が必要。夜間に強くなる傾向。
神経を取る処置が必要な場合が多い。
●咬むとズキンとする、あるいは持続する鈍い痛み
咬合性の亀裂や根尖性歯周炎、深い虫歯の疑い。
●複数の歯が同時にしみる/口全体がしみる
歯磨き過多や研磨剤の使用、薬剤性の一時的反応、全身性の要因を疑う。
●発熱や腫れ、膿が出る、顔面の腫脹がある
緊急性の高い感染。早急に受診が必要。
◎よくある原因と見分け方
●知覚過敏(エナメル摩耗や歯周退縮)
症状:冷たいものや風で短時間鋭い痛み。
見分けポイント:歯頸部のざらつきや根露出、歯磨き習慣。
●楔状欠損
症状:歯の根元にくさび形の欠損があり、冷刺激で鋭くしみる。
見分けポイント:歯頸部にV字状の削れが見える。
●二次う蝕(詰め物の周囲の虫歯)
症状:咬合時や冷温刺激で痛む。見た目に段差や変色があることが多い。
●歯髄炎・根尖性歯周炎
症状:熱い物で悪化、夜間痛、叩くと痛い、腫脹や発熱。
見分けポイント:冷温検査で強い反応、レントゲンで根尖陰影。
●咬合性の亀裂(クラック)
症状:特定の咬み合わせで鋭い痛みが出たり消えたりする。
見分けポイント:咬合時痛、咬合色の観察で亀裂が示唆される場合あり。
◎ 家で今すぐできる応急ケア(15分〜48時間の対応)
●刺激直後の対応
冷水でやさしくうがいして異物を除去する。強いうがいや熱湯は避けた方がいいでしょう。
●一時的な緩和策
ノンステロイド系の鎮痛薬を規定量服用(持病や常用薬がある場合は自己判断せず確認)して構いません。
●詰め物が外れた・欠けた時
出血がある場合は清潔なガーゼで圧迫止血。外れた破片は清潔な容器に保管して来院時に持参してください。
●噛むと痛む場合
痛む側で噛まないようにし、柔らかく温度差の少ない食品を摂りましょう。
●知覚過敏っぽい場合のホームケア
低研磨性の知覚過敏対応歯磨き粉を使用しましょう。強い力での歯磨きを避ける。
フッ化物配合製品の使用で症状が緩和することがあります。
●口腔衛生維持
優しくブラッシングし、刺激の少ないうがい薬で短期間ケアしましょう。刺激の強い市販薬の頻用は避ける。
◎受診までに準備しておくと診察が早く進む情報
- 症状の記録:痛みの始まった日時、誘因(冷・熱・咬合など)、持続時間、増悪時間帯(夜間など)。
- 既往・服薬:抗凝固薬や免疫抑制剤の有無、最近の歯科治療の履歴。
- 持参品:外れた詰め物や破片、痛みのある歯がわかる口腔写真(スマホ撮影で可)。
- 伝えるべきこと:痛みの程度(例:日常生活に支障があるか)、熱・腫れの有無、既往症。
◎歯科で行う検査と代表的な治療
- 診査:視診、打診、冷温検査、咬合検査、必要に応じてレントゲン撮影。
- 短期処置:感作抑制剤の塗布、接着による一時的な欠損封鎖、抗菌薬や鎮痛薬の処方(感染が疑われる場合)。
- 根本治療:知覚過敏なら再石灰化・歯肉の再付着促進、虫歯や二次う蝕は充填や被覆、歯髄炎が進行していれば根管治療。亀裂や歯根破折があれば保存不可の場合もあり、抜歯や補綴の検討が必要。
- 予防ケア:研磨剤の見直し、フッ化物やシーラント、生活習慣の改善指導。
FAQ
- Q: 冷たい物で一瞬だけしみるがすぐ治る。受診は必要?
- A: 頻度が少なければまず家庭での自己管理でよいが、回数が増える・持続する場合は受診した方がいいでしょう。
- Q: 知覚過敏用歯磨きはどれくらいで効く?
- A: 継続使用で数週間から1か月程度で効果が出ることが多いです。
- Q: 夜間に痛みが強くなる場合は?
- A: 歯髄炎の可能性が高く、早期受診を推奨します。
以上、歯がしみる時の原因や対処法、ケアについてのお話でした。
どういう風にしみるのか、よく状態を確認してその症状にあったケアをするのが大切です。
ご参考にしてみてくださいね(﹡ˆᴗˆ﹡)
こんにちは。
10月に入りたいぶ涼しくなってきました。
過ごしやすい時期が長く続くといいですよね( ´ω` ):
さて今回は、「口臭の原因は“歯”だけじゃない?胃・舌・ストレスとの関係と対策」というお話をしたいと思います(﹡’ω’﹡)ノ
多くの人が気になる口臭。
ご自身でも気になる方も多いと思いますが、家族や身近な人に指摘されたらショックですよね…( ;ᴗ; )
「歯はちゃんと磨いてるのに…」
口臭は、自分では気づきにくく、他人には言いづらいデリケートな悩み。
そして実は、原因は“歯”だけではないことが多いのです。
この記事では、口臭の種類・原因・対策を総合的に解説します!

☆口臭の主な分類と特徴☆
● 生理的口臭
- 原因:起床時・空腹時・緊張時など
- 特徴:一時的で自然に消える
● 病的口臭(口腔由来)
- 原因:歯周病・舌苔・むし歯など
- 特徴:持続的で強い臭いがある
● 病的口臭(全身由来)
- 原因:胃腸障害・糖尿病・副鼻腔炎など
- 特徴:特有の臭いがある(例:アセトン臭)
● 心因性口臭
- 原因:ストレス・不安・緊張など
- 特徴:実際には臭っていないこともある(自己臭症)
どういった原因からの口臭なのかを把握するのが大切です( •̀∀•́ )b!
◎歯科でできる口臭対策とは?
- 歯周病・むし歯の治療(炎症や膿の除去)
- 舌苔の除去(舌ブラシの使い方指導)
- 口腔乾燥の改善(唾液分泌促進)
- 定期的なクリーニングとメンテナンス
- 口臭測定器による数値化と説明
◎ 歯科以外の原因と対応
●胃腸の不調
逆流性食道炎や胃炎などが原因になることも。内科との連携が必要。
●副鼻腔炎・鼻づまり
鼻腔から口腔へ膿が流れ込むことで、特有の臭いが出ることがあります。
●糖尿病・肝疾患
代謝異常による特有の口臭(アセトン臭など)が出ることも。
●ストレス・緊張
唾液の分泌が減り、口腔内が乾燥して臭いが強くなる傾向があります。
◎セルフケアでできること
- 水分補給をこまめに(口腔乾燥予防)
- 舌ブラシを使って舌苔を除去
- 食後のうがい・フロス習慣
- ストレス管理(睡眠・運動・呼吸法)
口臭は、原因を正しく見極めることで、改善できる症状です!
「歯は磨いてるのに…」と悩む方こそ、歯科でのチェックが第一歩になります。
必要に応じて医科との連携も行いながら、あなたの不安を一緒に解消していきましょう( • ̀ω•́ )b ✧
こんにちは。
今日は歯科レントゲンは本当に安全なの?という疑問についてお話したいと思います(´︶` )ノ

★よくある不安
「レントゲンって放射線が心配…」
「妊娠中でも撮って大丈夫?」
こうした疑問に、科学的根拠と歯科医師としての配慮をもって答えることが、患者さんの安心につながります。
放射線量と安全性について
★ 放射線量の目安
● デンタルレントゲン(口腔内)
約0.01〜0.02mSv
● パノラマレントゲン(顎全体)
約0.03〜0.05mSv
● セファロレントゲン(頭部)
約0.01〜0.03mSv
● 歯科用CT
約0.1〜0.5mSv
● 胸部X線
約0.1mSv
● 東京〜NY往復の飛行機
約0.2mSv
● 自然放射線(年間)
約2.4mSv
※健康被害が懸念されるのは年間100mSv以上とされており、歯科レントゲンはその数百分の一以下です。
つまり歯科でのレントゲンは、リスクの限りなく低い量といえます。
★妊娠中の対応と安全性
- 歯科レントゲンは口腔領域のみを撮影するため、腹部への影響はほぼありません。
- 鉛の防護エプロンを着用することで、さらに被ばくを最小限に抑えます。
- 最新のデジタルレントゲン機器では、従来のアナログ機器よりも約1/5〜1/10の放射線量で撮影可能です。
なので妊娠中でも問題ないと言われております。
★ なぜレントゲンが必要なのか?
・目に見えない部分の診断に不可欠
むし歯の進行度、根の状態、骨の吸収、親知らずの位置などは、肉眼では確認できません。
・治療の精度を高めるための情報源
正確な診断が、無駄な治療や再発のリスクを減らすことにつながります。
◎安心して受けられる歯科レントゲン
歯科レントゲンは、非常に低線量で安全性が高い検査です。
正しい知識を持つことで、不要な不安を減らし、より安心して治療に臨むことができます。
気になることがあれば、いつでもご相談ください。
私たちは、患者さんの安心と納得を第一に考えています(*˘︶˘*)
こんにちは。
もうすぐ9月なのにまだまだ暑い日が続いておりますね。
最近当院に飾ってあったお花をご紹介します♪
色とりどり、季節を感じられて院内がパッと明るくなるので
生花は患者さんからもよく褒めていただきますv(´∀`*v)
残暑が厳しいですが、元気に頑張りましょう(´,,•ω•,,`)◝















こんにちは。
8月の休診日についてお知らせです(*´∀`*)ノ
12日(火)~15日(金)は夏期休診となります。
よろしくお願い申し上げます。

こんにちは。
暑い日が続いており日中外に出るのが嫌なくらいですね( ;ᴗ; )
さて今日は、噛む力が全身にどう関わってくるのか。
お口の健康と全身の健康はかなり大きな影響があることをお話したいと思います( •̀∀•́ )b
噛む力が弱くなると、将来どうなる?〜噛む力と全身の健康〜
噛む力、意識していますか?
多くの人が「歯が痛い」「入れ歯が合わない」などの不便を感じながらも、実はその「噛む力」が全身の健康に影響することには気づいていません。実は、“噛めないこと”は身体にも心にも、じわじわとダメージを与えるのです。
「噛む力が、病気の9割を遠ざける」なんて本も出ているくらいです( ⊙⊙)!!
噛む力が弱くなる原因とは?
- 加齢による筋力低下
- 歯の欠損や不適合な入れ歯
- 歯周病による歯のぐらつき
- 咬合(噛み合わせ)の異常
- 噛む習慣の減少(柔らかい食事ばかりなど)
噛む力が弱いと起こる健康問題とは?
●認知機能の低下
噛む刺激は脳への血流を促す重要な要素。研究では噛む力が弱い人ほど認知症のリスクが高まることも報告されています。
●骨格や姿勢への影響
噛む力は顎だけでなく、首・背中・全身の筋肉バランスにも関係します。噛み合わせの不調が姿勢の崩れにつながることも。
●食事の質と栄養バランスの低下
噛めないと柔らかいものばかりを食べるようになり、咀嚼による消化サポートが減り、栄養吸収も悪化します。
●意欲・QOLの低下
「うまく食べられない」「食事が楽しくない」ことで気分の落ち込みや社交意欲の低下につながる可能性も。
噛む力を維持するためにできること
◎定期的な歯科検診
歯周病やむし歯を早期に発見し、歯の喪失を防ぐことが第一。
◎咬合バランスの確認と調整
歯ぎしり・食いしばりなどがある場合、咬合調整やマウスピースの使用が効果的。
◎失った歯の早期補綴
ブリッジや入れ歯だけでなく、インプラントなど噛む力の回復に優れた補綴方法を選ぶことも重要。
◎噛む筋肉のトレーニング
ガムを一定時間噛む、口を大きく開けて発声するなど、口腔周囲筋を意識したエクササイズも有効。
しかし、こちらに関しては元々噛む力が強い方もいらっしゃいます。
その場合硬いものをたくさん食べたりするのはそれによって歯が割れたりする場合もあるので一概にはいえません。
噛む力は、健康の土台です!(๑•̀ㅂ•́)و✧
歯があるから噛める――これは当たり前のようで、実は大切な「資産」です!
噛む力を維持することは、健康寿命を延ばすための鍵。

歯を失わないように治療や定期検診は最も大事だといえるでしょう。
「噛む力=人生の質」と考えて、今できるお口のケアを始めましょう(*´∇`*)ノ
こんにちは。
今日から7月ですね!今年も半分終わってしまったなんてびっくりですよね(゚Д゚)
じめじめとした暑さで、過ごしにくい日々ですが
お身体お気をつけてお過ごしください( ´ω` ):
さてみなさんは、口内炎ができたらどうしていますか?
”治るまで待つ、ビタミン剤を服用する、バランス良く栄養を取る”
などでしょうか?
もちろん正しい対処法ですが、それでも治らない、もしくは痛みがひどくて早く治したい!
と言った場合は、歯科での口内炎治療があります(•᎑•)ノ

歯科での口内炎治療には、
軟膏の処方またはレーザー治療(またはその両方)があります。
お口の中に軟膏を塗るの?と思われる方もいるかもしれませんが、口の中に塗る前提で作られているので、
意外と流れずに留まってくれますよ(*´∇`*)
軟膏で済む程度だったらそれで大丈夫ですが、
時には痛みを伴い、食事や会話に支障をきたすこともあります。
そんな時には「レーザー治療」が効果的です!
その仕組みやメリットについて詳しくご紹介します。
《レーザー治療とは?》
レーザー治療は、特殊な光エネルギーを使用して患部を治療する方法です。
歯科では、口内炎の痛みを軽減し、治癒を早めるために活用されています。
◎レーザー治療の主なメリット
・痛みの軽減 レーザー光が神経の興奮を抑えるため、当てた直後から痛みが軽減します
・治癒の促進 レーザーは血流を促進し、組織の再生をサポートする為、早く治ります
・即効性 治療後すぐに痛みが軽減し、症状の緩和が期待できます
・非侵襲的 注射や切開が不要で、負担が少ないため安心して治療を受けられます
・感染リスクの軽減 レーザーが殺菌効果もある為、感染予防にも役立ちます
◎レーザー治療が適しているケース
・痛みが強く、日常生活に支障がある場合
・口内炎が頻繁に繰り返す場合
・他の治療法で改善が得られない場合
などが挙げられます。
治療時間は10分程度で終わります。

レーザー治療は、痛みを軽減し、早期回復を目指すための有効な手段です。
口内炎でお悩みの方は、ぜひ歯科医院での相談を検討してみてくださいね(^O^)
なお、2週間以上治らない場合は、口内炎ではなく他の疾患の可能性もあります。
長引く場合は早めに医療機関を受診しましょう(`・ω・´)b